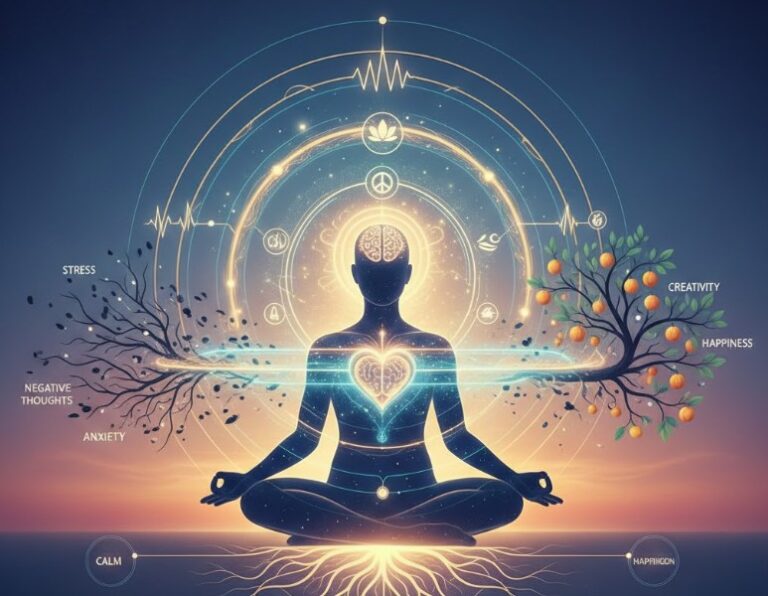タイムスリップ!鎌倉時代のお坊さん「栄西」が中国で学んだ「お茶の超パワー」とは?
『喫茶養生記』に隠された「五臓のバランス」と「健康長寿」の秘密を解き明かそう!
ようじょうくんと探る「お茶のチカラで健康長寿!」、いよいよ本格スタート!
前回は、この連載で何が学べるのか、そして「養生」や「喫茶養生」ってどんなことなのかを紹介したよね。
今回の主役は、鎌倉時代に活躍したお坊さん「栄西(えいさい)」。
彼が中国で体験した「お茶の超パワー」の秘密に迫っていくよ!
今から800年以上も前の中国で、栄西は何を見て、なぜお茶を「万病薬」とまで呼んだんだろう? そのヒミツを一緒に探ってみよう!
栄西、中国へ!仏教と「お茶」の旅
栄西は、日本の仏教(特に禅宗)を深く学ぶために、当時とても進んでいた国、中国(宋という国)へ二度も旅をしているんだ。今のように飛行機もない時代に、大きな船に乗って、命がけの航海だったはず。どれだけ仏教を学びたかったのかが伝わってくるよね。
でも、栄西が中国で学んだのは、仏教の教えだけじゃなかったんだ。彼は、中国の人々の暮らしや、当時の最先端の知識にも触れたんだよ。その中で、栄西の目に飛び込んできたのが、「お茶」が人々の健康に深く関わっているという驚きの事実だったんだ!
当時の中国には、日本とは比べものにならないくらい進んだ医学があったんだって。お医者さんが病気を治すための技術も、薬の種類もたくさんあった。でも、そんな高度な医療があるにも関わらず、栄西は一つの「疑問」を抱いたんだ。それは、「なぜ、こんなに医学が進んでいるのに、病気で苦しむ人が減らないんだろう?」ということ。
病気になってから治療するだけでは、なかなか健康な体は維持できない……そう感じた栄西は、ある中国の考え方に注目したんだ。それが、「未病を治す(みびょうをなおす)」という考え方なんだよ。
「未病を治す」って何?病気になる前の「予報」をキャッチ!
「未病(みびょう)」って言葉、聞き慣れないかもしれないね。これは、「病気ではないけれど、健康でもない、なんとなく調子が悪い状態」のことを言うんだ。
例えば、
「なんだか体がだるいな」
「ちょっと食欲がないな」
「いつもより眠い気がするな」
「集中できないな」
こんな時って、まだ病院に行くほどじゃないけれど、元気いっぱいの状態とは言えないよね? これがまさに「未病」の状態なんだ。
中国の昔の人は、こう考えたんだって。
「病気になってから薬を飲んだり治療したりするのは、喉が渇いてから井戸を掘り始めたり、戦いが始まってから武器を作り始めたりするのと同じだ。それでは遅すぎる!」ってね。
だから、「未病を治す」というのは、病気のサインが出始めたら、それが本格的な病気になる前に、早めに手当てをしよう! という考え方なんだ。
体からの小さな「調子悪いよー」という予報をキャッチして、すぐに対処することが、本当の健康につながるんだね。
栄西は、この「未病を治す」という考え方こそが、人々が健康に長く生きるための大切なカギだと気づいたんだ。そして、その「未病を治す」のに、お茶がとても効果的なのを知ったんだよ!
お茶は「養生の仙薬」!?『喫茶養生記』の驚きの宣言
栄西が日本に帰ってきてから書いたのが、みんなも知ってる『喫茶養生記』だ。この本の始まりには、とっても有名な言葉が書かれているんだ。
「茶は養生の仙薬なり。延齢の妙術なり。」
この言葉を、みんなにも分かりやすく言うと、
「お茶は、健康に生きるための、まるで魔法の薬のようだ! 寿命を延ばす、素晴らしい方法でもあるんだ!」
ってことなんだよ! すごい宣言だよね!?
なんで栄西は、ここまで自信を持ってお茶を「仙薬」と呼んだんだろう? その理由の一つに、昔の人が抱いていた「不老不死(ふろうふし)」への憧れがあるんだ。
みんなは、昔の中国の皇帝、秦の始皇帝(しんのしこうてい)って知ってるかな?
彼はお金持ちで権力もあって、何でも手に入れられたけれど、唯一手に入れられなかったのが「永遠の命」だった。だから、不老不死になれる「仙薬」を探すために、遠い海に徐福(じょふく)という人を送り出した、っていう伝説があるんだ。
そんな昔から、人間は「いつまでも若々しく、元気でいたい」
「病気にならない体になりたい」って強く願ってきたんだね。
栄西は、そんな人間の願いを叶える「仙薬」のような存在として、お茶に注目したんだよ。お茶には、病気を防ぎ、体を元気にして、できるだけ長く健康に生きるためのパワーが秘められている! そう確信したんだね。
「五臓のバランス」が健康のひみつ!
栄西が『喫茶養生記』で特に大切にしている考え方があるんだ。それは、私たちの体の中にある「五臓(ごぞう)」のバランスを整えること。
「五臓」っていうのは、私たちの体の中にある5つの大切な臓器のことだよ。
◆肝臓(かんぞう):怒りの感情と関係したり、体の毒素を分解したりする、化学工場みたいな役割。
◆心臓(しんぞう):喜びの感情と関係したり、血液を全身に送るポンプの役割。
◆脾臓(ひぞう):考えることと関係したり、食べ物から栄養を吸収する役割(※東洋医学では消化器系全体を指すことが多いよ)。
◆肺臓(はいぞう):悲しみの感情と関係したり、呼吸で体の中に新鮮な空気を取り入れる役割。
◆腎臓(じんぞう):恐れの感情と関係したり、体の水分や老廃物を調整する役割。
これらの五臓は、それぞれがバラバラに働いているわけじゃなくて、お互いに助け合ったり、影響し合ったりしながら、バランスを取り合っているんだ。まるで、オーケストラの楽器みたいにね。どの楽器も、音程やリズムがバラバラだと変な音楽になっちゃうように、五臓のバランスが崩れると、体も心も調子が悪くなっちゃうんだ。
栄西は、この五臓の中でも、特に「心臓」が一番大切だと考えたんだ。
心臓は、五臓のリーダーのような存在で、心臓が元気じゃないと、他の臓器も病気になりやすくなると説いたんだよ。
心臓と「苦味」、そして「お茶」の関係
さて、ここでクイズだよ!
Q.栄西は、心臓が元気になるためには、どんな味の食べ物や飲み物が良いって言ったと思う?
答えは……
「苦味(にがみ)」なんだ!
みんなは苦いものが好きかな? ピーマンとかゴーヤとか、ちょっと苦手な人もいるかもしれないね。でも、昔の中国の人は、それぞれの臓器には相性のいい味があると考えていたんだって。そして、心臓には「苦味」がぴったりだとされていたんだ。
ところが、普段の食事では、甘いものやしょっぱいもの、辛いもの、酸っぱいものはよく食べるけれど、苦いものを食べる機会って、あんまり多くないよね。だから、心臓は他の臓器に比べて、元気になれるチャンスが少ない!と栄西は考えたんだ。
そこで、栄西が注目したのが、まさに「お茶」だったんだ!
お茶って、飲むとちょっぴり苦いよね?
この苦味こそが、心臓を元気にするためにとても大切だと、栄西は言ったんだ。中国では、お茶を飲む習慣が昔からあったから、中国の人たちは心臓が丈夫で長生きしている人が多い!と栄西は考えたんだよ。
つまり、栄西は、
「五臓のバランスを整えることが健康長寿の秘訣だ!」
「特に心臓が大切で、心臓には苦味がいい!」
「だから、毎日お茶を飲んで苦味を摂りなさい!」
という、とっても論理的な結論を出したんだね。
お茶は本当に「万病薬」なの!?現代科学の答え
栄西が「諸薬はそれぞれの病気だけに効くけれど、お茶は万病に効く薬になる」とまで言った「万病薬」という言葉。今から800年以上も前に、どうしてそんなことが分かったんだろう?
実は、栄西の時代には、今のような顕微鏡や科学分析の機械はなかった。だから、彼はお茶を飲んだり、中国の人々の様子を観察したりする中で、経験的に「お茶はすごい!」と感じたんだ。
でも、すごいことに、栄西の言った「万病薬」という考え方は、現代の科学によって次々と証明されているんだよ!
お茶には、みんなも聞いたことがあるかもしれない、「カテキン」や「テアニン」といった、体に良い成分がたくさん含まれているんだ。
カテキン:この成分は、風邪のウイルスをやっつけたり、体のサビを防いだりする力があるんだ。最近の研究では、がんの予防に役立つ可能性も報告されているんだよ! まさに「病気にかかりにくい体」を作るための成分だね。
テアニン:この成分は、心を落ち着かせたり、集中力を高めたりする力があるんだ。勉強で疲れた時や、なんだかイライラする時に、お茶を飲むとホッと落ち着くのは、このテアニンのおかげなんだよ。
他にも、お茶にはビタミンCやE、食物繊維など、たくさんの栄養が含まれているんだ。これらが協力し合って、体の調子を整えたり、老化を防いだり、おなかの調子を良くしたり、アレルギーを抑えたり、本当にいろんな働きをしてくれるんだよ。
だから、栄西が「お茶は万病薬だ!」と言ったのは、決して大げさなことじゃなくて、「お茶を毎日飲むことで、体のバランスが整い、病気にかかりにくく、元気に長生きできるよ!」っていう、彼なりの最高のメッセージだったんだね。
「お茶を一服」に込められた想い
普段、お茶を飲む時に「お茶を一杯いかがですか?」って言うことはあっても、「お茶を一服(いっぷく)いかがですか?」って聞くことは少ないよね? でも、茶道の世界では、抹茶を一杯飲むことを「一服」って言うんだ。
これって、不思議だと思わない? なんで「一杯」じゃなくて「一服」なんだろう?
実は、昔の中国では、「服」という言葉は、「薬を飲むこと」に使うことが多かったんだって。例えば、薬を飲むことを「服用(ふくよう)」って言うよね。これは今も使われている言葉だ。
だから、「お茶を一服」という表現には、昔の人がお茶を「薬のように大切に、ありがたく飲むもの」として扱っていた気持ちが込められているんじゃないかな、って言われているんだ。栄西も『喫茶養生記』で、お茶を飲むことを「服」という言葉で表現している箇所があるんだよ。
昔の人が、心と体を健やかに保つために、お茶をどれだけ大切にしていたか、この「一服」という言葉からも伝わってくるよね。
まとめ:栄西が残した「喫茶養生」の大きな一歩
栄西が中国で学んだ「喫茶養生」の考え方は、まさに「病気になる前に体を整える」という、現代にも通じる予防医学の考え方だったんだ。
お茶は「養生の仙薬」であり、「寿命を延ばす妙術」である。
五臓のバランス、特に心臓を苦味のあるお茶で整えることが大切。
お茶には、現代科学でも証明される、病気を防ぎ体を元気にする「万能薬」のようなパワーがある。
「一服」という言葉には、お茶を薬のように大切にする昔の人の想いが込められている。
こんなにもすごい「お茶の超パワー」を、栄西は日本に持ち帰ってくれたんだね。
でも、栄西が日本に帰ってきてから、お茶はすぐにみんなに広まったわけじゃないんだ。次回の「お茶のチカラで健康長寿!」では、そんな栄西の死後、お茶がどのように日本で広まっていったのか、そしてなぜ栄西が「お茶の神様」と呼ばれるようになったのか、そのヒミツを探っていくよ!