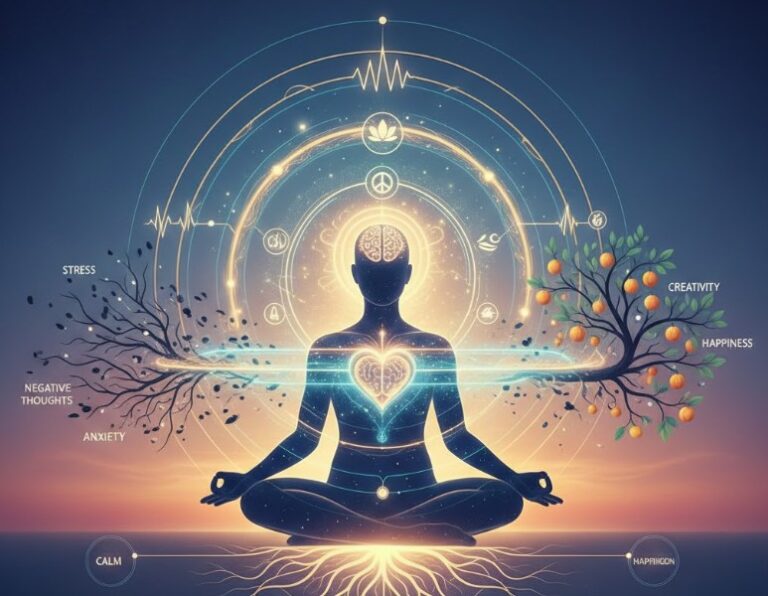贅沢すぎるお茶会!?中世の日本でお茶が「遊び」に変わったワケ
宇治茶🍵の誕生から「一服一銭」の庶民のお茶まで、時代の変化をたどる!
ようじょうくんと探る「お茶のチカラで健康長寿!」、今回は日本の歴史の中でも特に面白い時代、鎌倉時代から室町時代にかけてのお茶のお話だよ。前回は、栄西(えいさい)が「茶祖(ちゃそ)」と呼ばれるすごい理由を5つ紹介したよね。栄西は、お茶を「病気を防ぐ薬」として日本に広めようとしたんだった。
でも、彼の死後、お茶は思わぬ方向へ進んでいくんだ。なんと、貴族や武士の間で、贅沢な「遊び道具」になっていったんだよ! でもその一方で、お茶が庶民の暮らしにも広まっていく、大切な変化も起きたんだ。
一体、中世の日本でお茶に何が起こったんだろう? ようじょうくんと一緒に、そのヒミツを探ってみよう!
栄西の願いを受け継いだ人たち
栄西が亡くなった後も、彼が日本に持ち帰ったお茶の種や、お茶を飲む習慣は、お坊さんたちの間で大切に受け継がれていったんだ。
その中でも特に大切な人物が、明恵上人(みょうえしょうにん)というお坊さんだよ。彼は栄西と直接会って、お茶の苗(なえ)をもらったと言われているんだ。そして、京都にある栂尾(とがのお)の高山寺(こうさんじ)というお寺に、そのお茶の木を植えたんだよ。この高山寺には、今も「日本最古の茶園(ちゃえん)」という石碑が立っているんだ。
明恵上人は、お茶が体にいいことを広めるために、あるユニークなアイデアを思いついたんだ。それは、お茶を沸かす釜(かま)の側面に「茶の十徳(じっとく)」という、お茶が持つ10のいいことを刻んだ、という伝説だよ。
「茶の十徳」には、こんなことが書かれていたんだって。
仏様が守ってくれる(諸仏加護)
体の五臓の調子が良くなる(五臓調和)
親孝行につながる(孝養父母)
悩み事がなくなる(煩悩消除)
長生きできる(寿命長遠)
眠くならない(睡眠自除)
災いがなくなり、長生きできる(息災延命)
神様が近くにいてくれる(天神随身)
いろんな神様が守ってくれる(諸天加護)
死ぬ時に心が乱れない(臨終不乱)
ね、お茶を飲むことで、体も心も、さらには神様との関係まで良くなるなんて、昔の人がどれだけお茶にすごいパワーを感じていたかが分かるよね。明恵上人は、栄西とは違う宗派(華厳宗)のお坊さんだったけれど、お茶を通じて人々の健康や幸せを願う気持ちは同じだったんだ。
お茶が庶民に広まるきっかけ「大茶盛式」
お茶が、一部の偉い人だけでなく、もっと多くの人々に広まるきっかけを作ったお坊さんもいるんだ。それが、奈良の西大寺(さいだいじ)の叡尊(えいそん)というお坊さんだよ。
叡尊は、病気で苦しむ庶民を助けたいという優しい気持ちを持っていたんだ。彼は、お寺でたくさんの人たちにお茶を振る舞う「大茶盛式(おおちゃもりしき)」という行事を始めたんだよ。
「大茶盛式」は、直径が40センチもある、とっても大きなお茶碗で抹茶を点(た)てて、それをみんなで回し飲みする、というユニークな行事なんだ。今でも西大寺で毎年行われているんだよ。
叡尊は、お酒を飲まないという仏教の教えを守るために、お酒の代わりにこの大茶盛式でお茶を振る舞ったんだ。そして、病気で困っている人たちに、お茶を「薬」として与えたんだ。これを「施茶(せちゃ)」と言うんだよ。
このように、栄西の死後も、お茶は「養生」、つまり「健康を保つための薬」として、お坊さんたちによって広められていったんだね。
お茶が「遊び」に変わる!?鎌倉〜室町時代の変化
ところが、時代が進むにつれて、お茶の使われ方は少しずつ変わっていくんだ。鎌倉時代から室町時代になると、特に偉い人たちの間で、お茶は健康のためというよりも、「贅沢な遊び」の道具になっていったんだよ。
そのきっかけの一つが、「唐物(からもの)」ブームだ。
「唐物」っていうのは、中国から輸入された、とっても高価で珍しい品物のこと。お茶を飲むための茶碗(ちゃわん)や、お花を飾る花瓶(かびん)、お香を焚(た)く香炉(こうろ)なんかがそうだよ。当時の偉い人たちは、これらの唐物を手に入れるために大金を使い、みんなで集まって、誰が一番すごい唐物を持っているかを見せびらかしたりしたんだ。
そして、お茶の席で行われたのが、「闘茶(とうちゃ)」という遊びだ。
「闘茶」は、いろんな産地のお茶を飲み比べて、どのお茶がどこで作られたかを当てるゲームなんだ。今でいうと、ブランドの洋服やスニーカーを自慢し合ったり、限定のおもちゃを競い合ったりするのに近いかもしれないね。
この頃のお茶会は、お茶そのものの味を楽しむというよりは、高価な茶道具を見せ合ったり、闘茶で盛り上がったりする社交の場になっていったんだ。お茶が、人々の「遊び」や「自慢」の道具になってしまったんだね。
偉いお坊さんの「ちょっと待った!」:夢窓礎石の言葉
お茶がどんどん贅沢な遊びになっていく様子を見て、心配したお坊さんもいたんだ。それが、室町時代の初めに活躍した、夢窓礎石(むそうそせき)という偉いお坊さんだよ。
彼は、当時の将軍(日本のリーダー)だった足利直義(あしかがただよし)に、お茶のあり方についてこんなふうに教え諭しているんだ。その言葉は、『夢中問答(むちゅうもんどう)』という本に書かれているよ。
「みんながお茶を愛するのは、ご飯の消化を助けたり、気分を良くしたりして、健康を保つためなんだ。薬も分量が決まっているように、お茶も飲みすぎると体に良くない。昔の偉い人たちがなぜお茶を好んだかというと、眠気を覚まし、心を落ち着かせて、学問や修行に集中するためだったんだよ。」
「でも、今の世の中の人がお茶をもてなす様子を見ると、とても健康のためとは思えない。それどころか、お金を無駄に使い、仏教の教えまで廃れてしまう原因になっている。だから、お茶を好む気持ちは同じでも、その人の心の持ち方によって、体に良いか悪いかが決まるんだ。」
どうかな? 夢窓礎石は、「お茶は本来、健康や修行のためのものだったはずだ!」って、当時の人たちの贅沢すぎるお茶会をビシッと批判したんだね。彼は、お茶が「養生」という大切な視点から離れて、ただの「遊び」になってしまったことをとても残念に思っていたんだ。
この頃には、栄西が強調した「喫茶養生」の考え方が、偉い人たちの間ではほとんど忘れられてしまっていたんだね。
庶民のお茶文化の始まり:「一服一銭」の登場!
貴族や武士の間では、お茶が贅沢な遊びになっていたけれど、その一方で、お茶がもっと身近なものとして、庶民の暮らしにも広がり始めた、という大きな変化もあったんだ。
室町時代に入ると、お寺の門前などで、「一服一銭(いっぷくいっせん)」というお茶のお店が登場するんだよ。「一服一銭」っていうのは、その名の通り、お茶を一杯、たった一銭で売ってくれる、っていうことなんだ!
当時の東寺(とうじ)というお寺の記録には、1403年(今から約600年前!)に、門前でお茶を売っていた人たちが、お寺と交わした「誓約書(せいやくしょ)」が残っているんだ。
そこには、
「お寺の入り口の石段のそばに住まないこと」
「お寺の中に茶道具を置かないこと」
「お寺の火や水を使わないこと」
といったルールが書かれていたんだって。
この記録から分かるのは、当時の東寺の門前には、お茶を売る人たちがたくさんいて、お寺も彼らを無視できないくらい、お茶の商売が盛んだったってことだよね。お寺にお参りする人や、観光に来る人たちが、休憩がてら気軽にお茶を飲んでいた様子が目に浮かぶようだね。
風俗画が語る庶民のお茶の姿
この頃の庶民の暮らしを描いた絵(風俗画(ふうぞくが))にも、お茶を飲む人たちの姿が描かれているんだよ。
例えば、「観楓図屏風(かんぷうずびょうぶ)」という古い屏風(びょうぶ)絵には、お茶を売るおじいさん(売茶翁(ばいさおう)というんだ)や、座って気楽にお茶を楽しむ庶民の姿が描かれているんだって。
この絵に描かれているお茶は、お湯で煮出して作る「煎じ茶(せんじちゃ)」だったと考えられているよ。栄西が広めた抹茶とは違って、もっと手軽に作れるお茶だったんだね。
しかも、この庶民のお茶は、ただ喉の渇きを癒(いや)すだけじゃなかったんだ。当時の売り子さんたちは、こんな歌を歌っていたんだって。
「痰(たん)を切らいてお声の出で候。虫の薬も加え加えて煎じたる煎じ物。
陳皮(ちんぴ)、乾薑(かんきょう)、葉甘草(はかんぞう)も加えて煎じたる煎じ物。」
どうかな? これって、
「痰が切れて声が出るようになるよ」
「虫下しにもなる薬草も入ってるよ」
「ミカンの皮(陳皮)やショウガ(乾薑)、甘草(かんぞう)なんかも入ってるよ」
って言っているんだ。
つまり、庶民の間で売られていたお茶は、病気を治したり、体の調子を整えたりする「薬用のお茶」だったんだね。
偉い人たちが「遊び」のためにお茶を楽しんでいた一方で、庶民は「薬」としてお茶の価値を見出し、生活に取り入れていたんだ。
まとめ:中世のお茶は二つの道を進んだ
今回の連載で見てきたように、鎌倉時代から室町時代にかけて、日本のお茶は大きく二つの道を進んだんだ。
一つは、貴族や武士の間で、高価な道具を使った「贅沢な遊び」として発展した道。この道は、のちに「茶の湯(ちゃのゆ)」という日本独自の素晴らしい文化へとつながっていくんだ。
もう一つは、庶民の間で、「手軽な薬」として、毎日の暮らしに溶け込んでいった道。この道は、「一服一銭」のような形で、多くの人々の健康を支えたんだ。
栄西が「喫茶養生」を提唱した願いは、一時的に忘れられたように見えたかもしれないけれど、形を変えながらも、庶民の暮らしの中に息づいていたんだね。