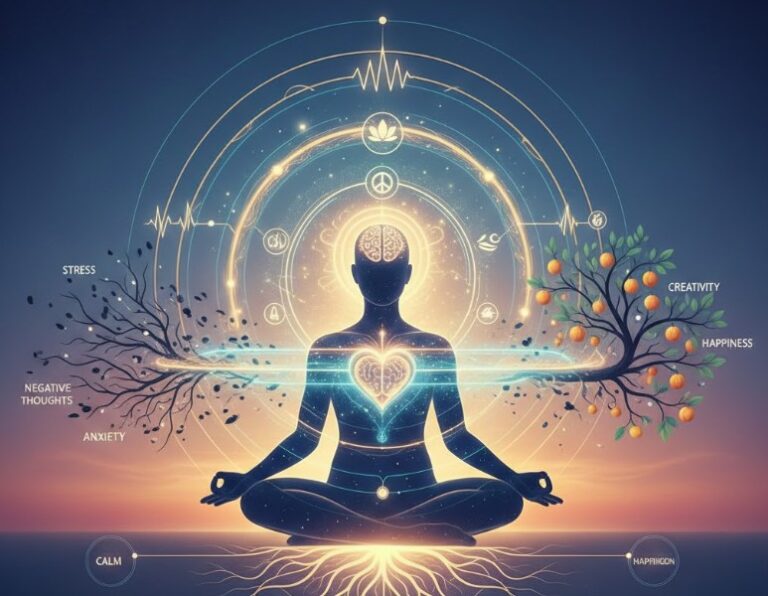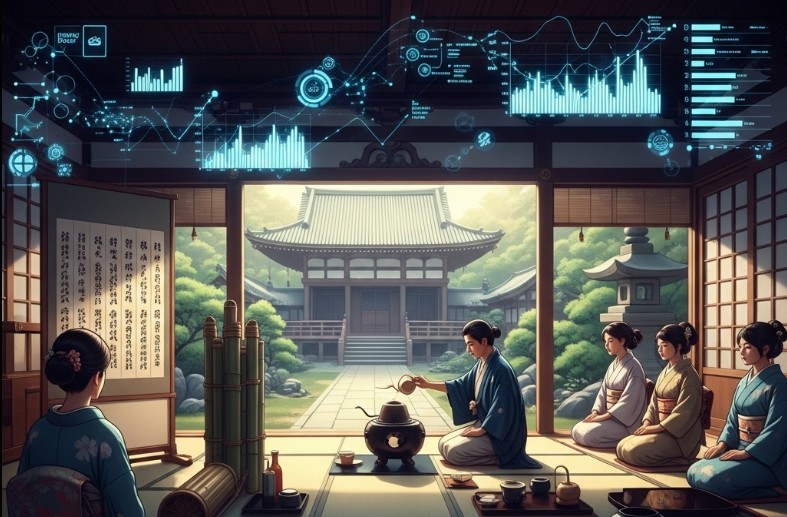
戦国の武将から大金持ちまで!お茶を愛した有名人はなぜ長生きだったの?
統計データで解き明かす「お茶と寿命」の驚きの関係!
【養生くん】と探る「お茶のチカラで健康長寿!」。
前回は、鎌倉時代から室町時代にかけて、お茶が貴族の「贅沢な遊び」になったり、庶民の「薬」として広まったりしたお話をしたよね。お茶がいろんな形で人々の暮らしに溶け込んでいったことが分かったかな?
今回は、いよいよ今回の連載で一番ワクワクするテーマかもしれないよ!
「お茶を愛した人たちは、本当に長生きだったの?」
「病気や感染症にも強かったって本当?」
これらのギモンに答えるために、今回は白井宗佐博士が論文で調べた、歴史上の有名人たちのデータを見ていくよ!
戦国時代の武将から、有名なお茶の先生、そして大金持ちまで、お茶を愛した「茶人(ちゃじん)」と呼ばれる人たちの寿命や病気について、統計データを使って、ようじょうくんが分かりやすく解説するね。さあ、一緒にデータの海へ飛び込もう!
「茶人」ってどんな人たち?データ分析の対象を紹介!
白井博士は、お茶と健康の関係を調べるために、ずーっと昔から現代までのお茶に深い関わりを持っていた有名人たちをたくさん調べてくれたんだ。これを、今回の連載では分かりやすく「茶人」と呼ぶことにしよう!
博士が調べた「茶人」には、大きく分けて2つのグループがあるよ。
【茶人1】グループ(457人):これは、お茶を「茶道(さどう)」として深く学んだり、政治や文化で利用したりした人たちだよ。たとえば、あの織田信長や、茶道を完成させた千利休(せんのりきゅう)、有名な茶道の家元(いえもと)の先生たち、そしてお茶を愛した大金持ち(「数寄者(すきしゃ)」って言うんだ)などが含まれるんだ。彼らは主に抹茶(まっちゃ)を飲んでいた人たちだね。
【茶人2】グループ(87人):こちらは、「煎茶道(せんちゃどう)」という、抹茶とは違う形でお茶を楽しんだ人たちだよ。江戸時代に広まった煎茶(せんちゃ)というお茶を愛飲した、文人(ぶんじん)と呼ばれる学者や芸術家、そしてお茶の生産を頑張った人たちなどが含まれるんだ。
これらの茶人たちは、お茶と全く縁のない普通の人たちと比べて、毎日とってもたくさんお茶を飲んでいたと考えられているんだ。たとえば、有名な茶人である小堀遠州(こぼりえんしゅう)という人は、なんと生涯で390回以上もお茶会を開いた記録があるんだって!
一番多い年には、1年に91回も!
つまり、3日に1回はお茶会をしていた計算になるんだ。お茶会では、濃いお茶(濃茶)と薄いお茶(薄茶)を飲むから、1回のお茶会で飲むお茶の粉の量は、合わせて約6グラムになる。もし毎月91回お茶会をしていたら、月に60グラム以上のお茶を摂取していたことになるんだよ。
これ、今の日本人が1ヶ月に飲む緑茶の量(平均約21グラム)と比べると、3倍近くも多いんだ! ね、すごい量だよね?
これだけお茶をたくさん飲んでいた人たちは、本当に長生きだったのかな?
さっそくデータを見てみよう!
茶人たちの平均寿命は「当時としては驚異的」だった!?
まずは、【茶人1】グループの寿命を見てみよう。下の表は、時代ごとにお茶を愛した人たちの平均寿命をまとめたものだよ。
| 時代 | 平均寿命(歳) | 人数 |
| 鎌倉時代 | 72.63 | 8 |
| 室町時代 | 67.47 | 15 |
| 安土桃山時代 | 59.38 | 21 |
| 江戸時代 | 63.90 | 219 |
| 明治時代 | 63.43 | 53 |
| 大正時代 | 69.31 | 29 |
| 昭和(戦前) | 77.44 | 34 |
| 昭和(戦後) | 77.20 | 44 |
| 平成時代 | 83.29 | 34 |
どうかな? 鎌倉時代や室町時代は、まだデータが少ないけれど、70歳前後という数字が見えるよね。当時の日本の平均寿命と比べてみよう。
下の表は、だいたいの時代の日本の平均寿命だよ。
| 時代 | 西暦 | 平均寿命(男性) | 平均寿命(女性) |
| 鎌倉時代 | 1185-1333 | 約61.4歳(※上流階級) | |
| 室町時代 | 1394-1572 | 約60.8〜61.1歳(※上流階級) | |
| 江戸時代 | 1675-1740 | 37.1歳 | 37.6歳 |
| 明治時代 | 1891-1898 | 42.8歳 | 44.3歳 |
(※これらの平均寿命のデータは、調査方法が時代によって違うため、あくまで参考として見てね。)
この表と比べると、茶人たちの平均寿命、特に鎌倉時代の栄西(75歳)、明恵(60歳)、そして90歳まで生きた叡尊(えいそん)などは、当時の日本人としては、本当に長生きだったことが分かるよね!
叡尊は、前回お話した西大寺の大茶盛式を始めたお坊さんだよ。
江戸時代になると、一般の人の平均寿命は30歳代から40歳代と、とても低くなるけれど、茶人たちは60歳代と、かなり長生きしていることが分かるね。これは、茶人たちが、将軍や大名、裕福な商人といった「上流階級」の人たちが多かったことも関係しているかもしれない。彼らは、良い食べ物を食べられたり、衛生的な環境で暮らせたり、病気になってもお医者さんにかかれるなど、当時の人々より恵まれた生活を送れたから、長生きできた、という理由も考えられるよね。
でも、ちょっと考えてみてほしいんだ。上流階級の人たちって、おいしいものをたくさん食べたり飲んだりして、運動不足になったりする「贅沢病」にかかることもあったはずだよね? 今でいう「生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)」みたいな病気のことだ。
それなのに、茶人たちは一般の人より長生きだったのはなぜだろう?
白井博士の論文によると、調べた457人の茶人の中で、80歳以上まで生きた人が約24%(109人)もいたんだって! そして、70歳以上まで生きた人は約52.5%(240人)と、半数以上がお年寄りと呼ばれる年齢まで生きたんだ。これは当時としては、本当にすごいことなんだよ!
茶人たちは病気とどう戦った?「持病」と「死因」のデータ
次に、茶人たちがどんな病気にかかり、何が原因で亡くなったのかを見ていこう。これは、お茶が本当に「養生」に役立ったのかを知るための大切なデータだよね。
まず、日本の人々の死因が、時代とともにどう変わってきたかを見てみよう。
| 年代 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 昔(1899年頃) | 肺炎・気管支炎 | 脳血管疾患 | 結核 |
| 現代(2019年) | 悪性新生物(がん) | 心疾患 | 老衰 |
昔は、肺炎(はいえん)や結核(けっかく)といった「感染症(かんせんしょう)」(菌やウイルスでうつる病気)で亡くなる人が多かったんだ。
でも、今では、がん(悪性新生物)や心臓病(心疾患)、脳卒中(脳血管疾患)といった「生活習慣病」で亡くなる人が増えているんだね。
これは、食生活や運動習慣など、毎日の暮らし方が病気に大きく影響するようになった、ということだ。
では、茶人たちはどうだったんだろう?
白井博士が調べた146人の茶人のデータを見てみると、亡くなった原因(死因)の約75%が、先ほど挙げたような肺炎、脳血管疾患、結核、がん、心疾患、胃腸炎、老衰といった病気だったんだ。
特に注目したいのは、生活習慣病で亡くなった茶人が、全体の約46%もいたということ。
これは、上流階級の茶人たちも、現代の私たちと同じように、食生活やストレスなどからくる生活習慣病と無縁ではなかった、ということだね。
でも、病気を抱えながらも長寿を全うした茶人もいたんだ。その一人が、松永安左エ門(まつなが やすざえもん)という人だよ。彼は「電力の鬼」と呼ばれた大実業家で、茶名は「耳庵(じあん)」。なんと96歳まで生きたんだ!
耳庵は、10代でコレラという怖い感染症にかかって入院して以来、その後もたびたび入院する記録が残っているんだ。70歳代半ばでは大腸炎(だいちょうえん)を患(わずら)ったり、晩年には肺にカビが感染する病気(アスペルギールス病)にかかったりもしたんだって。
でも、彼がこれほど長生きできたのはなぜだろう? 主治医の先生によると、耳庵は、
新しい薬には副作用があるかもしれないから、ビタミンをしっかり摂って体力をつけたり
毎日散歩をしたり、毎日欠かさず、自分で作った肉(赤身)の佃煮(つくだに)を食べて、タンパク質をしっかり摂ったり、ぐっすり眠るために、睡眠薬や少しのお酒を飲んだり
といった、規則正しい生活習慣を徹底的に守っていたんだって!
そして、晩年、晴れた日にはお茶を点てて楽しむ「茶人」としての生活を送り、お茶がいつもそばにあったんだ。
耳庵の人生を見ると、お茶を飲む習慣が、彼がこれだけの病気を乗り越えて長生きできたことと、少なからず関係していたんじゃないかな、って想像できるよね。
感染症にも強かった!?パンデミックを乗り越えた茶人たち
さらに驚きのデータがあるんだ。それは、世界中で多くの人が命を落とした「感染症の大流行(パンデミック)」の時代に、茶人たちがどうだったか、ということ。
みんなは、今から約100年前に世界中で大流行した「スペイン風邪」って知ってるかな?
これはインフルエンザの仲間で、第一次世界大戦の終わり頃(1918年~1920年)に世界中で猛威を振るい、なんと世界中で4000万人以上、日本でも38万人以上の人が命を落としたと言われているんだ。ワクチンも特効薬(とっこうやく)もなかった時代だから、本当に恐ろしい病気だったんだよ。
また、19世紀にはコレラという細菌性の感染症も、世界中で何度も大流行して、たくさんの人が亡くなったんだ。
そんな死の病が流行した時代を生き抜いた茶人たちは、どうだったんだろう?
白井博士の論文によると、スペイン風邪が流行した時期に亡くなった茶人は、データがはっきりしている中では、たったの3人しか確認できなかったんだって!
しかも、この3人も、直接スペイン風邪で亡くなったと確定しているのは1人で、他の2人は持病の腎臓病が悪化したことが死因だったんだ。
考えてみてほしい。当時の日本人が約38万人も亡くなっているのに、茶人たちの死亡者がこれだけ少ないのはなぜだろう?
もちろん、茶人たちは上流階級の人が多かったから、一般家庭よりも衛生的な環境が整っていた、という理由も考えられるよね。手洗いやうがい、マスクといった当時の政府が推奨した「予防」対策も、徹底して行えたのかもしれない。
でも、それだけじゃないかもしれないんだ。
前回の連載で話したように、お茶にはカテキンという強力な「抗菌作用(こうきんさよう)」があるんだ。菌やウイルスと戦ってくれる力のことだね。そして、お茶を飲むことで、体の免疫力(めんえきりょく)が高まる可能性も、現代の研究で示されているんだ。
スペイン風邪のように、特効薬がない時代に多くの人が命を落とした中で、お茶を日常的に飲んでいた茶人たちが、感染症にかかりにくかったり、かかっても重症化しにくかったりした可能性があるとしたら、それは「喫茶養生」の大きな効果と言えるんじゃないかな?
つまり、茶人たちは、意識していたかどうかは別として、毎日お茶を飲むことで、「病気にかかる前の予防」や、「病気になっても回復する力」といった「生命力(せいめいりょく)」を、知らず知らずのうちに高めていたのかもしれないんだね。
まとめ:お茶は「生きる力」を養う秘訣だった!
今回の連載で見てきたように、白井博士の論文からは、お茶を愛した「茶人」たちが、当時の平均寿命よりも長く生き、病気や感染症にも比較的強かったという驚きの傾向が見えてきたね。
これは、「お茶を飲む」という日々の習慣が、単に喉を潤すだけでなく、私たちの体が持つ「生きる力」=「生命力」を養い、病気を未然に防ぐ「養生」の素晴らしい方法だった、という栄西の考え方を強く裏付けるものだと言えるんじゃないかな。
もちろん、お茶だけが長寿の秘訣ではなかっただろう。バランスの取れた食事、適度な運動、ストレスをためない心の健康、そして恵まれた生活環境など、様々な要因が複合的に影響し合っていたはずだ。でも、その中でも「喫茶習慣」が、病気にならない体を作り、元気に生きる力を高める上で、重要な役割を果たしていた可能性が、このデータから読み取れるんだ。
次回「お茶のチカラで健康長寿!」では、日本だけじゃなくて、世界中でお茶がどう広まり、健康とどう関わってきたのかを見ていくよ。紅茶の国イギリスや、長寿の街として知られる香港(ホンコン)など、世界の「喫茶養生」の歴史を旅してみよう!