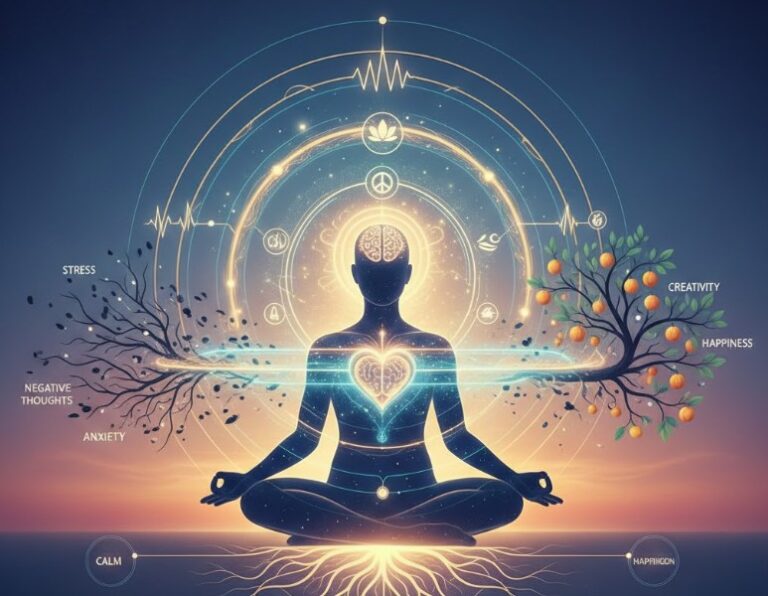紅茶の国イギリスも、長寿の香港も!世界が愛する「お茶」の健康術
日本だけじゃない!世界の「お茶と養生」の歴史を旅しよう!
ようじょうくんと探る「お茶のチカラで健康長寿!」。
前回は、日本の歴史上の「茶人(ちゃじん)」たちが、お茶をたくさん飲むことで、どれだけ長生きして、病気にも強かったか、という驚きのデータを見てきたよね。
お茶が、私たちの「生きる力」を養う「養生(ようじょう)」に役立っていたことが分かったかな?
今回は、舞台を日本から世界へと広げてみよう!
お茶って、もともとは中国やインドのあたりが生まれ故郷なんだ。そこから、どうやって世界中に広まっていって、それぞれの国でどんな「健康術」として愛されてきたんだろう?
ようじょうくんと一緒に、紅茶の国イギリスや、長寿の街として知られる香港(ホンコン)を旅して、世界の「お茶と養生」の歴史を探ってみよう!
はじめは「薬局」で売られていた!?紅茶の国イギリス
「お茶の国」って聞くと、どこを思い浮かべるかな?
日本の抹茶も有名だけど、世界で一番お茶を飲んでいる国の一つが、実はイギリスなんだ! イギリスといえば、アフタヌーンティーに代表される紅茶文化がとっても有名だよね。
でも、イギリスにお茶が初めて伝わった時、今のようにカフェで気軽に飲めるようなものじゃなかったんだ。なんと、最初は「薬局(やっきょく)」で売られる「薬」として、とても高い値段で取引されていたんだって!
イギリスより先に中国とおつき合いをしていたポルトガルという国の宣教師(せんきょうし)が、中国で「お茶」という飲み物が、体にとてもいい「薬効(やっこう)」がある、と言われているのを見て、記録に残しているんだ。彼は、お茶を飲んで「苦い」と感じたけれど、「体に効くらしい」という情報をヨーロッパに持ち帰ったんだね。
イギリスにお茶が広まる大きなきっかけを作ったのは、17世紀にポルトガルからイギリス王室に嫁いできたキャサリンというお姫様なんだ。彼女がお茶好きで、イギリスの王室や貴族の間で、お茶を飲む習慣が広まっていったんだよ。
イギリスの「お茶博士」が広めた健康パワー!
お茶がイギリスに伝わった当初は、あまりにも高価だったので、貴族しか手に入れられない、珍しい「薬」という感じだった。でも、このお茶の「すごい効能(こうのう)」を、もっとたくさんの人に伝えようとした「お茶博士」がいたんだ。それが、オランダのボンテクー博士だ。
彼は、胃の調子を整えたり、便通を良くしたり、熱がある時に薬よりもお茶を飲むことをすすめたりしたんだって。
ボンテクー博士は、お茶を「万能薬」だと考えていて、なんと1日に50〜60杯も飲むと熱が下がる、なんて言っていたんだよ! 今考えるとびっくりする量だけど、高熱の時に水分をたくさん摂って、汗をかいて毒素を出す、っていうのは、今の医学でも理にかなっていることなんだ。
でも、こんなに「お茶は健康にいいぞ!」って言う人ばかりじゃなくて、「お茶なんてニセモノの珍しいものだ!」とか「体を悪くするぞ!」なんて批判するお医者さんもいたんだって。新しいものが広まるときには、いつも賛成派と反対派がいるものだよね。
大ヒットした「お茶の広告」!
そんな中、イギリスの紅茶文化が爆発的に広がる決定的なきっかけを作ったのが、あるお茶屋さんの「広告」だったんだ。
ロンドンの大商人、トーマス・ギャラウェイという人が、こんな「お茶の広告」を新聞に出したんだよ。
「この素晴らしい葉(お茶)は、昔から知識と知恵で知られる東洋の国々では、同じ重さの銀の2倍の値段で売られています。そして、この飲み物には、信じられないほどの効能と効果があります。」
そして、広告にはお茶の具体的な効能がズラリと並んでいたんだ。
体を元気に活発にする!
頭痛やめまい、だるさを和らげる!
腎臓(じんぞう)や尿(おしっこ)の道をきれいにして、結石(けっせき)に効く!
目の炎症(えんしょう)を治し、視力(しりょく)を良くする!
疲れを取り、体をきれいにし、消化を助ける!
悪い夢を見なくなり、脳(のう)を休ませ、記憶力(きおくりょく)を強くする!
眠気を抑え、徹夜で勉強しても体に害を与えない!
どうかな? これって、栄西が『喫茶養生記』に書いたお茶の効能と、そっくりだと思わない?
ギャラウェイは、東洋で「お茶が薬として使われている」という情報を手に入れて、それを商売に活かしたんだね。
この広告が大ヒットして、ロンドンの街では、お茶が急速に庶民の間に広まっていったんだ。この頃、ロンドンではペストという恐ろしい伝染病が大流行したり、大火災が起きたりと、大変な時期だったんだ。そんな中で、お茶を飲む習慣が広まったのは、お湯を沸かして飲む紅茶が、菌の入った水を飲むよりも安全だったから、という理由も大きいと考えられているよ。
病気が蔓延(まんえん)する中で、煮沸(しゃふつ)したお茶を飲むことが、人々の命を守る大切な役割を果たしたんだね。こうして、お茶はイギリスの人々の健康を支え、やがて国のシンボルとなるほど、欠かせない存在になっていったんだ。
世界一の長寿の街、香港の「喫茶養生」
次は、日本のお隣、アジアに目を向けてみよう!
みんなは、世界で一番平均寿命が長い街がどこか知ってるかな?
それは、実は香港(ホンコン)なんだ! 日本も長寿国として有名だけど、香港はなんと6年連続で世界一の座に輝いたこともあるんだよ(※調査方法が変わってランキングからは外れたけど、香港が長寿の街であることは間違いないよ)!
香港の人たちが長生きな理由には、いろんなことが考えられるけれど、その一つに「お茶」が深く関係していると考えられているんだ。
香港の人たちが普段よく飲むお茶は、主に烏龍茶(ウーロンちゃ)やプーアール茶だよ。これらは「半発酵茶(はんかっこうちゃ)」と言われる種類で、油っぽい食事をした時に、脂肪(しぼう)の分解を助けてくれたり、消化(しょうか)を良くしてくれたりする効果があることで知られているんだ。中華料理って、油をたくさん使う料理が多いから、烏龍茶やプーアール茶は、まさに香港の人たちの食生活にぴったりなんだね。
「涼茶」ってなに?飲んで治す漢方薬!
でも、香港の「喫茶養生」で、特に面白いのが「涼茶(りょうちゃ)」という飲み物なんだ!
「涼茶」は、香港の街角のドリンクスタンドや、スーパーの缶ジュースコーナーでも売られている、香港の人たちにとってとっても身近な飲み物だよ。一見すると普通のお茶に見えるけれど、実はこれ、「漢方薬(かんぽうやく)」なんだ!
涼茶には、甘草(かんぞう)、仙草(せんそう)、スイカズラ、菊の花など、いろんな薬草がブレンドされているんだ。これらの薬草は、体の熱を取ったり、毒素を出したり、風邪を治したり、喉の渇きを癒したりと、古くから中国の伝統医学で使われてきた、すごい効能を持つものばかりなんだよ。
香港は、夏が長くて湿度が高い、とても暑い場所だよね。そんな気候の中で、香港の人たちは「上火(ションフォ)」といって、体の中に熱がこもって、口内炎ができたり、頭が痛くなったり、体調が悪くなる、という考え方があるんだ。
そこで、この「上火」を防ぐために、冷たい涼茶を飲むんだよ。涼茶は、体の中にこもった熱を冷まして、体のバランスを整えてくれる。まるで、体の熱さましのような役割を果たしているんだ。
「薬食同源」の知恵が生きる香港
涼茶が「お茶」という名前で、毎日の生活に溶け込んでいるのは、中国の昔からの「薬食同源(やくしょくどうげん)」という考え方が深く関係しているんだ。
「薬食同源」は、日本の「医食同源(いしょくどうげん)」とよく似ていて、「食べ物と薬はもともと同じもので、毎日の食事で健康を保つことが大切だ」という考え方だよ。
香港の人たちは、涼茶だけでなく、「亀苓膏(きりんこう)」というデザートも食べるんだ。これは「亀ゼリー」とも呼ばれているんだけど、亀の甲羅(こうら)の粉や、たくさんの漢方薬の材料を使って作られているんだ。これも、体をきれいにしたり、免疫力(めんえきりょく)を高めたりする効果があると言われているんだよ。
このように、香港の人たちは、お茶やデザートとして、日常的に漢方薬の成分を体に取り入れているんだ。これは、病気にならないように体を整える「未病(みびょう)」の考え方が、彼らの食生活の中に深く根付いている証拠だよね。
彼らの「飲茶(やむちゃ)」文化も、お茶と一緒に点心(てんしん)(軽食)を楽しみながら、家族や友達とコミュニケーションを取る、という、心と体の両方を「養生」する素晴らしい習慣なんだ。
まとめ:世界中で受け継がれる「お茶の健康パワー」
今回の連載では、日本のお茶の歴史から飛び出して、イギリスと香港の「喫茶養生」を見てきたね。
イギリスでは、お茶は最初は高価な「薬」として伝わり、やがて感染症から人々を守る飲み物として、国民全体に広まっていった。
香港では、お茶が日常の飲み物としてだけでなく、「漢方薬」の成分を含む「涼茶」や「亀苓膏」として、体のバランスを整える「養生」の知恵が深く根付いている。
国や文化は違っても、「お茶が人々の健康に役立つ」という考え方は、世界中で受け継がれてきたんだ。栄西が800年以上前に日本に伝えた「喫茶養生」の考え方が、こんなにも世界中の人々に共通する「健康の知恵」だったなんて、驚きだよね!
次回「お茶のチカラで健康長寿!」では、これまでの連載で学んできた知識を活かして、みんなが今日から始められる「ようじょうくん流」のお茶の健康習慣について、具体的にお話ししていくよ! お楽しみにね!