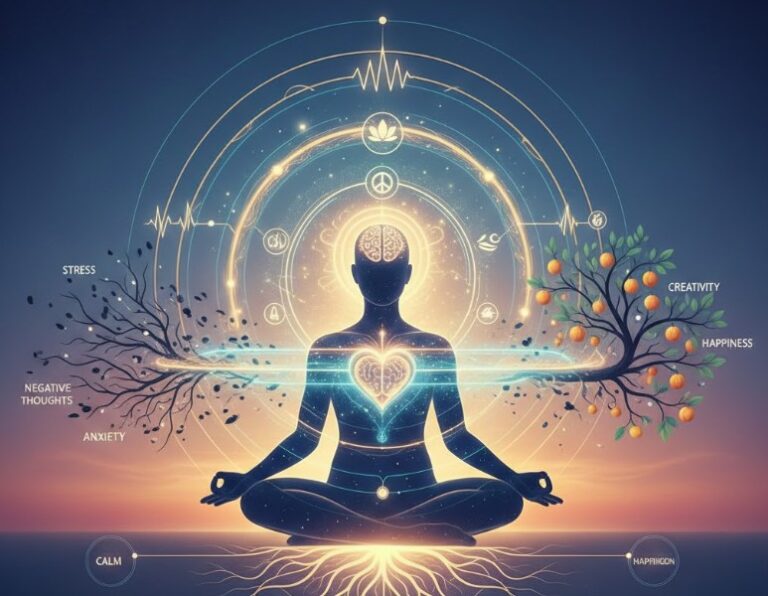800年前の「健康の神様」からのメッセージ!栄西の願いを今こそ受け取ろう!
なぜ『喫茶養生記』は現代に語りかけるのか?「未病」という考え方を深掘り!
養生くんと探る「お茶のチカラで健康長寿!」。
これまでの連載で、私たちは鎌倉時代のお坊さん、**栄西(えいさい)**が日本にお茶と「喫茶養生(きっさようじょう)」の考え方を伝えたこと、そして、その後の日本や世界でお茶がどのように広まり、人々の健康を支えてきたのかを見てきたよね。
今回は、この連載のまとめに向けて、もう一度栄西の気持ちにグッと近づいてみよう!
栄西が『喫茶養生記(きっさようじょうき)』という本に込めた「本当の願い」って、一体何だったんだろう?
そして、今から800年以上も前に書かれたその本が、どうして現代に生きる私たちに、こんなにも大切なメッセージを語りかけてくるんだろう?
そのカギは、前回も少し触れた「未病(みびょう)」という考え方にあるんだ。
ようじょうくんと一緒に、昔の人の知恵に隠された、現代の健康につながるヒントを探ってみよう!
「養生」の究極の目的は「生きる力」の維持!
みんなは「養生(ようじょう)」って聞いて、どんなイメージを持つかな? 病気にならないように気をつけること? 体に良いものを食べること? どれも正解だよね。
でも、栄西が『喫茶養生記』で伝えたかった「養生」には、もっと深く、大きな目的があったんだ。それは、ズバリ「生命力(せいめいりょく)を維持する」ということ!
「生命力」って何だろう? それは、私たちが生まれながらに持っている、「生きるためのパワー」のことだよ。病気と戦う力、疲れても回復する力、そして、成長していく力……。これらの「生きるためのパワー」を、できるだけ長く、力強く保ち続けることが「養生」の究極の目標なんだ、と栄西は考えたんだね。
人間は誰でも、いつかは終わりがくる。でも、どうせなら、できるだけ長く、元気いっぱいの状態で生きたい、って思うよね? そのために、病気になってから慌てて治療するだけでなく、病気になる前から自分の「生きる力」を養っておくことが、何よりも大切なんだ、と栄西は教えてくれているんだ。
栄西の「健康の神様」からのメッセージ:「未病を治す」
さて、この「生命力を維持する」という大きな目標を達成するために、栄西が特に大切にした考え方が、前回もお話した「未病を治す」というものだよ。
もう一度確認してみよう。「未病」というのは、「まだ病気と診断されるほどではないけれど、体がだるい、疲れやすい、食欲がないなど、健康とは言えない状態」のことだ。
想像してみてほしい。
風邪をひきそうになった時、「なんか喉が痛いな」「体がゾクゾクするな」と感じる時があるよね? これがまさに「未病」のサインなんだ。この時に、「大丈夫、まだ熱はないから!」と放っておくと、本格的に風邪をひいて、高熱が出たり、学校を休まなくちゃいけなくなったりすることもあるよね。
でも、「未病」のサインに気づいて、すぐに温かいお茶を飲んで体を温めたり、早めに休んだりすれば、ひどい風邪にならずに済むかもしれない。これが「未病を治す」ということなんだ。
栄西は、当時の中国で、病気になってから治療する「対症療法(たいしょうりょうほう)」(症状を抑える治療)だけでは不十分だと感じたんだ。彼は、「病気になってから井戸を掘り始めても遅い!」と、病気になる前の「予防」がどれだけ大切かを訴えたんだよ。
この「未病を治す」という考え方は、今、世界中の医療で注目されている「予防医学」や「ヘルスケア」の考え方と、そっくりだと思わない?
800年以上も前に、栄西がこんなに先進的な考え方を持っていたなんて、本当に驚きだよね! まさに彼は、私たちに健康のヒントをくれる「健康の神様」からのメッセージを届けてくれているんだ。
栄西は「医僧」だった!?『喫茶養生記』は医学書?
栄西は、お坊さんだったけれど、実は「医者」のような役割も果たしていたんだ。彼のようなお医者さんの心得(こころえ)を持ったお坊さんのことを、「医僧(いそう)」と呼ぶことがあるよ。
鎌倉時代は、戦乱や飢饉(ききん)、そして疫病(えきびょう)が大流行する、とても大変な時代だったんだ。たくさんの人々が病気で苦しみ、神仏に救いを求めていたんだよ。
そんな中で、栄西のような医僧たちは、貧しくて病院に行けない庶民(しょみん)のために、お茶を「薬」として与えたり、健康の知恵を教えたりしたんだ。彼らは、仏教の教えを広めるだけでなく、人々の病気を治し、苦しみを和らげるという、社会にとっても大切な役割を担っていたんだね。
だから、栄西が書いた『喫茶養生記』は、単なる「お茶の飲み方を紹介する本」ではなかったんだ。当時の最先端の医学知識や、中国の伝統医学の考え方を取り入れて、お茶の効能や養生の方法を体系的にまとめた、「当時の日本の医学書」と考えることもできるんだよ。
この本には、栄西の「日本の人々を病気から救いたい」「健康になって元気な毎日を送ってほしい」という、熱い願いが込められているんだね。
栄西の「草木国土悉皆成仏」と命の尊さ
栄西が信仰していた禅宗の教えには、「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」という言葉があるんだ。ちょっと難しいけれど、これは「草や木も、地球そのものも、そして石や自然現象も、この世に存在するすべてのものに『仏の心』、つまり尊い『命』が宿っている」という考え方なんだ。
人間だけが特別なのではなく、この地球上のすべての生き物、そして自然そのものが、尊い命を持っている。だから、それらを大切にすることが、お坊さんとしての使命なんだ、という教えなんだね。
この考え方から見ると、栄西がお茶の「養生」を大切にした理由が、もっと深く理解できるよね。彼は、お茶の木という「草木」にも命が宿っていて、そのお茶が人間に「生命力」を与え、病気から守ってくれることを知ったんだ。
つまり、お茶を飲むことは、単に体を元気にするだけでなく、「自分自身の命」という尊い存在を大切にする行為でもあったんだね。そして、病気で苦しむ人々にお茶を施すことは、彼らの「命」を救い、尊い生命を維持させるための、栄西なりのお坊さんとしての慈悲(じひ)の心だったんだ。
白井博士が解き明かす!お茶が持つ6つの「生命力アップ」パワー!
白井博士の論文では、栄西が大切にした「生命力」をさらに掘り下げて、お茶がこの「生命力」にどう影響する可能性があるのかを、次の6つの能力に分けて考えているんだ。
① 運動能力(うんどうのうりょく):走ったり、登ったり、体を動かす力のこと。
② 抗疲労能力(こうひろうのうりょく):疲れても、そこから回復する力のこと。
③ 老化緩和能力(ろうかかんわのうりょく):年を取るにつれて体が衰えるのを、ゆっくりにする力のこと。
④ 抗病能力(こうびょうのうりょく):病気にかかりにくいように、体を守る力のこと。
⑤ 闘病能力(とうびょうのうりょく):もし病気にかかってしまっても、病気と戦って打ち勝つ力のこと。
⑥ 健康回復能力(けんこうかいふくのうりょく):病気やケガから回復して、元の元気な体に戻る力のこと。
どうかな? これら「生きるためのパワー」って、どれも私たちにとって、とっても大切な能力だよね。そして、白井博士は、お茶を日常的に飲む「喫茶養生」が、これらの能力を高める可能性を秘めているんじゃないか、と考えているんだ。
これまでの連載で見てきた、長生きした「茶人」たちのデータや、感染症を乗り越えたお話、そして科学的に証明されているお茶の成分の効能は、まさにこの「生命力アップ」の可能性を示しているんだね。
まとめ:『喫茶養生記』は現代への「養生」ガイドブック!
今回の連載で、私たちは栄西の『喫茶養生記』が、単なる古いお茶の本ではないことが分かったよね。
病気になる前に体を整える「未病を治す」という先進的な考え方。
すべての人々の「生命力を維持する」という、栄西の深い願い。
そして、その願いを叶えるための「お茶の超パワー」!
栄西は、800年以上も前に、私たち現代人が抱える「どうすれば健康に長生きできるんだろう?」という悩みに、すでに答えを出してくれていたのかもしれない。彼の『喫茶養生記』は、まさに時代を超えて私たちに語りかける「養生ガイドブック」なんだね。
お茶を飲むという日々の小さな習慣が、私たちの「生命力」を養い、「未病」を防ぎ、最高の自分を生きるための大きなチカラになる。栄西が教えてくれたこの知恵を、今こそ私たちも受け取って、毎日の生活に取り入れていきたいね。
次回「お茶のチカラで健康長寿!」では、これまでの知識を活かして、みんなが今日から始められる「ようじょうくん流」のお茶の健康習慣について、具体的にお話ししていくよ! お茶選びから、おいしい淹れ方、そして楽しみ方まで、盛りだくさんの内容だから、お楽しみにね!