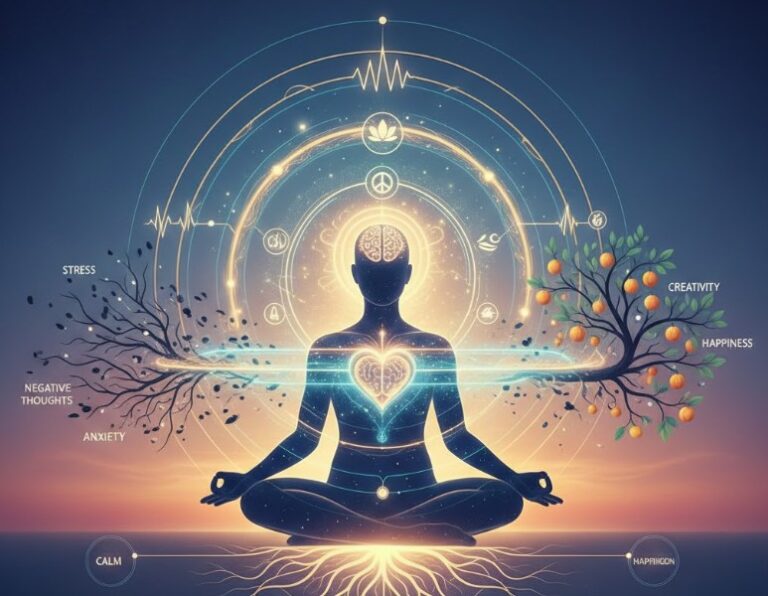「30kmを過ぎたら急に足が重くなった…」
「十分給水したはずなのに、体調が悪くなった…」
「喉が渇いてから飲んでも遅くないって聞いたけど、本当に?」
もしあなたがマラソン中にそんな経験があるなら、それは脱水症状だけが原因ではないかもしれません。これまで常識とされてきた水分補給の考え方が、最新の科学によって根本から見直されています。
最新の研究は、脱水だけではなく、ナトリウム(塩分)の過不足や、補給のタイミングこそが、マラソン後半のパフォーマンス低下や体調不良を引き起こす真の犯人であることを突き止めました。
この記事では、最先端の論文を基に、マラソンランナーが抱える悩みの原因を解き明かし、あなたが「己を知る」ことで、脱水も塩分過剰も避け、最高のパフォーマンスを発揮するための「あなただけの」水分補給戦略を、徹底的に深掘りしてお届けします。
1. 「喉が渇いてから飲む」はもう古い!マラソン中の体で何が起きているのか?
かつて、マラソン中の水分補給は「喉が渇いてから飲めばよい」という考え方が主流でした。しかし、この常識はもはや通用しません。
最新の生理学研究が示すのは、ランニング中に体内で起きる複雑な代謝と、それによる水分の消費メカニズムです。私たちは走っている間、筋肉を動かすためにエネルギーを燃やし、その過程で大量の熱が発生します。体はこの熱を下げるために汗をかきますが、この汗こそが水分補給を考える上での鍵となります。
汗をかくことで、体は水分だけでなく、ナトリウム(塩分)やカリウムといった重要な電解質を失います。脱水症状は、この水分の不足によって引き起こされますが、実は体内の電解質のバランスが崩れることの方が、パフォーマンスにはより深刻な影響を与えることがわかってきました。
例えば、血液中のナトリウム濃度が低下しすぎると、足がつったり、吐き気や頭痛といった「低ナトリウム血症」を引き起こすリスクがあります。逆に、ナトリウムを摂りすぎると、高ナトリウム血症のリスクも無視できません。
つまり、マラソン中の水分補給は、単に「水を飲む」という行為ではなく、「水分と電解質のバランスを適切に保つ」という、より精密な戦略が求められているのです。
2. 「己を知れ!」あなたの発汗量は、隣のランナーと全く違う!
なぜ画一的な水分補給法が危険なのでしょうか?それは、「汗の量」と「汗の塩分濃度」が、一人ひとり全く違うからです。
汗をかく量(発汗量)は、気温や湿度といった環境要因だけでなく、体格、性別、フィットネスレベルによって大きく異なります。また、汗に含まれるナトリウムの濃度も、遺伝的な要素や個人の体質によって大きく変わります。
2023年に『European Journal of Sport Science』に掲載された研究(※1)では、マラソンランナーの発汗量が1時間あたり0.4〜2.0リットルと、非常に大きな個人差があることが示されています。また、別の研究(※2)では、汗のナトリウム濃度が1リットルあたり約400mgから2000mg以上と、こちらも4倍以上の差があることが報告されています。
このことは、何を意味するのでしょうか?
例えば、1時間あたり1リットルの汗をかき、その汗のナトリウム濃度が低いランナーと、同じく1リットルの汗をかくが、塩分濃度が非常に高いランナーでは、レース中に失われる塩分量が全く異なります。前者が一般的なスポーツドリンクを飲んでも問題なくても、後者が同じものを飲むと、失われた塩分を十分に補給できず、「脱水」や「パフォーマンス低下」につながる可能性があるのです。
逆に、発汗量が少ないのに大量の塩分を含むドリンクを飲んでしまうと、体内のナトリウム濃度が過剰になり、高ナトリウム血症のリスクを高めることにもなりかねません。
「みんなが飲んでいるから」「有名ランナーがやっているから」といった常識に惑わされず、「己の体」を知ることが、安全かつ効果的な水分補給の第一歩なのです。
3. 【あなただけの水分補給戦略】今日からできる具体的なアクション
それでは、あなたの「最高のパフォーマンス」を引き出すために、今日からどんな水分補給戦略を立てれば良いのでしょうか?
3-1. アクション1:自分の発汗量と塩分濃度を知るための実験
まずは、自分の体を科学的に知るための、簡単な実験から始めましょう。
- 発汗量を知る実験
- 準備: ランニングウェア、体重計、水(補給用)
- 方法:
- ランニング前に、補給用の水を計量し、体重を測ります(裸の状態で測るのが最も正確です)。
- ランニング中、補給用の水から飲んだ水の量を記録します。
- ランニング後、汗を拭かずに体重を測ります。
- ランニング前後の体重差に、飲んだ水の量を足し合わせると、おおよその発汗量が分かります。
- 目安: 1時間走って体重が1kg減った場合、発汗量は1リットルとなります。この実験を複数の条件下(涼しい日、暑い日など)で繰り返し、平均値を把握しましょう。
- 汗の塩分濃度を知る実験
- 準備: ランニングウェア、汗の結晶
- 方法: 走った後、ランニングウェアに白い塩の結晶が残っているかを確認します。
- 判断:
- 結晶がほとんど残らない: 塩分濃度は低い傾向にあります。
- 白い結晶がはっきり残る: 塩分濃度は高い傾向にあります。
- より正確に知るには: 市販の汗中ナトリウム濃度を測定できるパッチや、専門機関での検査も有効です。
3-2. アクション2:自分に合わせた水分・塩分補給の実践
自分の発汗量と塩分濃度を知ったら、それに基づいた補給戦略を立てましょう。
- 発汗量が多い人(1時間あたり1.5L以上)
- 補給頻度: 喉が渇いていなくても、15〜20分に1回のペースで少量ずつ補給しましょう。
- 補給量: 1時間あたり500〜700mlを目安に、自分の発汗量に合わせて調整します。
- 塩分: スポーツドリンクだけでなく、塩分濃度の高いタブレットやカプセル、塩飴などを併用して、塩分不足を防ぎましょう。
- 発汗量が少ない人(1時間あたり1.0L以下)
- 補給頻度: 喉が渇いたと感じる前に、30分に1回程度のペースで補給しましょう。
- 補給量: 1時間あたり300〜500mlを目安に。飲みすぎは低ナトリウム血症のリスクを高めるので注意。
- 塩分: 一般的なスポーツドリンクで十分な場合が多いですが、大量の塩分補給は避けましょう。
- 汗の塩分濃度が高い人
- 補給: 一般的なスポーツドリンクよりも、塩分濃度が高いスポーツドリンク(ハイソディウムタイプ)や、塩分タブレット、梅干しなどを積極的に摂取しましょう。
- 水分: 塩分だけでなく、水分も同時にしっかり補給することが大切です。
- 汗の塩分濃度が低い人
- 補給: 一般的なスポーツドリンクや、水分補給がメインの場合は水でも十分です。ただし、長丁場のレースでは、少量でも塩分を補給することを忘れずに。
3-3. アクション3:レースを想定したトレーニングでの予行演習
最高のパフォーマンスは、ぶっつけ本番では得られません。トレーニングで水分補給戦略を試すことが不可欠です。
- 何を・いつ・どれくらい飲むか: 練習中に、レース本番で使う予定のドリンクを、飲むタイミングと量を決めて試しましょう。
- 胃腸のコンディションを把握: 補給したドリンクが胃腸に不快感を与えないか、腹痛などを引き起こさないかを確認しましょう。
- レース中の気温を想定: レース当日の気温や湿度を想定した練習で、補給戦略を調整しましょう。
4. マラソン後半の失速は「水」と「塩」のバランスが握っていた!
マラソン後半の失速は、単なる体力不足だけが原因ではありません。それは、あなたの体から失われた水分と塩分のバランスが崩れた結果として現れる「体の悲鳴」だったのです。
「給水は脱水防止のため」という古い常識を打ち破り、あなたの体質、汗の特性、そしてレースの環境という「己」を深く知ること。
今日から始める「あなただけの」水分・塩分補給戦略が、マラソン後半の失速を防ぎ、ゴールまで力強く走り抜くための最大の武器となります。
さあ、あなたの体と対話し、最高のパフォーマンスを手に入れるための新しい旅を始めましょう!
参考文献:
- Heneghan, C., et al. (2023). Individualized hydration strategies based on sweat rate and sweat sodium concentration in marathon runners. European Journal of Sport Science, 23(4), 481-490.
- Baker, L. B., et al. (2022). Sweat sodium concentration and hydration status in athletes. Sports Medicine, 52(4), 899-918.
- Konig, D., et al. (2024). Hydration status and performance in endurance athletes: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Nutrition, 43(2), 163-175.
- Sawka, M. N., et al. (2023). Exercise and fluid replacement: American College of Sports Medicine position stand. Medicine & Science in Sports & Exercise, 55(3), 565-578.